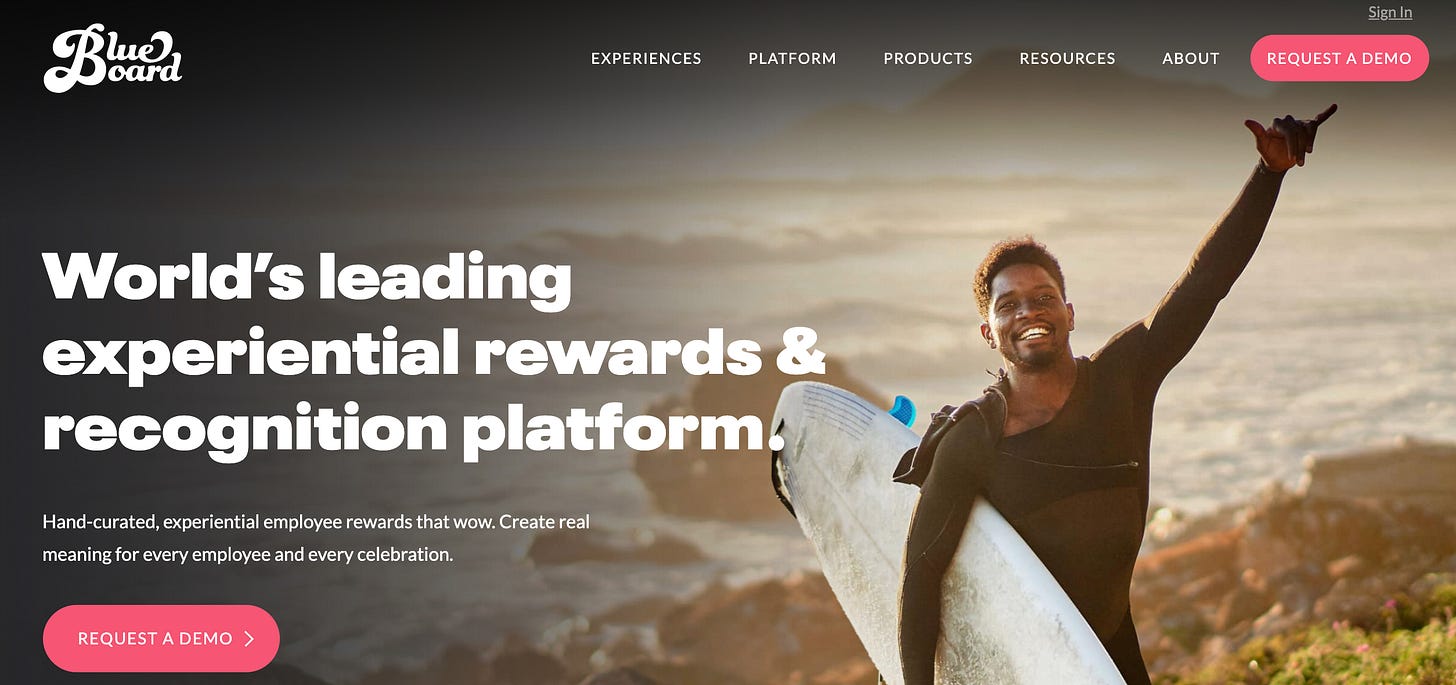9月も中盤に入り、2021年も残り3ヶ月少しですが、みなさま如何お過ごしでしょうか?私達が駐在している米国カリフォルニアではデルタ株が猛威を振い、GoogleやFacebookを始めオフィス再開時期を延期する企業も出てきています。リモートワークが常態化する中で、世界中で新しい働き方、従業員のモチベーションアップや社員同士のコミュニケーションの新しい形が模索されていると思います。今回のBlogではアメリカで新しい試みを行っているスタートアップや米国IT企業に勤める方から聞いたちょっとした工夫などをご紹介したいと思います。
「商品券や表彰状ではなく”体験”をプレゼント」BlueBorad
「みんな誰かの”ヒーロー”だ」Bonusly
「”カード一枚”から始まる有意義な会話」BIG TALK
1.「商品券や表彰状ではなく”体験”をプレゼント」BlueBorad
<ポイント>
・従業員への褒賞に、ギフトカードや表彰状の代わりに”体験”をプレゼント
・”体験”を社内で共有することで、社員の仕事以外の一面を知ることができる
・”体験”の手配はBlueboardがフルサポート。世界70カ国300社以上が利用
カリフォルニアに本社を置くスタートアップBlueboardは、従業員への勤続年数に応じた褒賞や誕生日、年間目標達成のプレゼントにギフトカードや現金などでは、従業員にとってあまり意味がないと考えています。Blueboardは、企業が社員に記憶に残る有意義な”体験”を提供すると、従業員のモチベーションやエンゲージメントが長期的に高まっていくと考えソリューションを開発。更に、金銭的報酬は従業員の間で話題にしにくいですが、体験型ギフトであれば共有しやすく (Blueboardのプラットフォームには写真や文章を共有できる機能もついています) 、社員の仕事以外の一面を知ることもできます。
提供される”体験”はBlueboardがパートナー企業と開発を進めており、例えば裏庭にDIYで温室を作るような家庭内での体験から、カイトサーフィンを学んだりジンベイザメと泳いだりするような冒険まで、世界中のすべての従業員にオンリーワンの冒険を提供できる仕組みを持っています。
すでにGoPro、Salesorce、P&Gなど世界70カ国、300社以上で利用されており、在宅勤務が続き孤独を感じたり燃え尽き症候群になりつつ社員に単純に”金銭(モノ)”を与える時代から”体験(コト)”を提供するという新しい価値提供が、これからの職場には求められていくかもしれません。
2.「みんな誰かのヒーローだ」Bonusly
<ポイント>
・従業員間で好きなタイミングで報酬ポイントを送りあえる
・貯めたポイントが形になる
・”感謝”しあう職場文化を作り上げる
コロラドに拠点を置くBonuslyは毎月会社から配布される報酬ポイントを、同僚への感謝の気持ちとして送りあえるプラットフォームを提供しています。日本でも紙の「ありがとうカード」のようなもので同様の取り組みを行っている企業もあるかもしれませんが、そのデジタル版になります。デジタルプラットフォーム上で管理されているので、組織のみんながその記録や関係性を見ることが可能で、過去に遡ってその人がどんな人とどんな仕事をして感謝されていたのかや、どんな人と連携して日々業務を行なっているのかもすぐに可視化できます。
また溜まったポイントは現金やギフトカードの他、慈善団体への寄付にも交換可能になっており企業のSDGsの活動の一環としても注目されています。
フリートライアルもあるので筆者の所属する6人のチームでも少し試すことができました。実際のインターフェースはシンプルで、チャットツールのSlackとも連携できる手軽に始めることができます。
Bonuslyの仕組みは特に在宅勤務が当たり前になり、自分のアウトプットが誰にとって役に立ったか見えづらくなったからこそ求められている仕組みかもしれません。上司との定期的な面談やフィードバック以外に、日々の小さな同僚からのフィードバックや感謝が、従業員の孤独や燃え尽きつつある疲弊した心を癒してくれます。なかなか感謝を口にするのは照れくさいかもしれませんが、「ありがとう」の気持ちを簡単なコメントとポイントで送りあうことで、遠隔地で業務を行なっていてもチームの一体感や結束はより強くなるのではないでしょうか?どこにいても、お互い感謝しながら良い仕事をしていく、そんな環境をBonuslyは手助けしてくれます。
3.「”カード一枚”から始まる有意義な会話」BIG TALK
<ポイント>
・より意味のある雑談を行える質問を「紙のカード」で提供
・TEDでの公演動画は650万回以上再生、世界中でワークショップが行われている
・ランダムにカードを選び質問に答えるだけで、より人間性を理解できる
ここまでご紹介した、BlueboardやBonuslyはデジタルの力を使い、コロナ時代における新しいコミュニケーションの形を提供しています。このようなソリューションが米国では数多く生まれていますが、最後にご紹介するのは、あるオンラインカンファレンスで米国IT企業に勤める方から聞いた、社員同士のコミュニケーションを深める”ちょっとした工夫”です。
多くのミーティングがオンラインに移行し、実際のオフィスであった雑談(SMALL TALK)が極端に少なくなったと言われています。そのため雑談をオンラインでも奨励する動きもありますが、その雑談をより意味のあるものにすることで、お互いをより深くしろいうという取り組みをしているのがBIG TALKです。
BIG TALKはより意味のある雑談を行える質問を紙のカードで提供しています。私が聞いた”ちょっとした工夫”とは、その米国IT企業の週次オンラインチームミーティングの冒頭、みんなで一人一枚このカードを引いてカードの質問に答えるところからミーティングを始めることでした。それだけのことですが、カードの質問がその人の人間性を浮かび上がらせる質問になっており、そのような会話をした後の会議ではより活発な意見交換ができるようになったと教えてくれました。
そんな力を秘めるBIG TALKの考案者、Kalina Silvermanさんは大学に入学した当初、いろんな人と会い会話をしましたが、どこか孤独感や表面的な関係性しか築けていないことに気がつきます。そこであまり意味のない世間話に終始するのではなく、よりお互いの人生にとって意味のある質問(彼女はそれをBIG TALKと名付けます)をすることにしました。
この取り組みの中で彼女は驚くべき発見をします。うわべだけの世間話では決して得られなかった絆を初対面の人と感じることができ、見知らぬ人との交流は、今も続く友情へと発展していきました。彼女は自分のBIG TALKの経験を伝えるために、“What do you want to do before you die?(死ぬ前に何をしたいですか?)”という質問をした様子を収めた映像をYouTubeに投稿しました。数週間のうちに動画は拡散し、Huffington Post、USA Today、Business Insider、Right this MinuteなどがBig Talkについての特集記事を掲載しました。彼女はTEDにも招待されて講演を行い、その動画の再生回数は650万回を超えています。
How To Skip the Small Talk and Connect With Anyone | Kalina Silverman | TEDxWestminsterCollege
数千円で買えるカードデッキですが、その中には人生を変えるきっかけになる質問もあるかもしれません。
まとめ
今回のBlogでは、未だ続くコロナの猛威により在宅勤務が続く中、様々な手段で社員のモチベーションやコミュニケーション活性化させる米国スタートアップのツールや工夫をご紹介させていただきました。共通するのは、想像以上に在宅勤務は社員に孤独感や疲弊感をもたらしており、それに対応するために画一的な対応ではなく、より社員一人ひとりの価値観や意見に寄り添った対応やこまめなフィードバックの必要性。そして人間の本質として誰かに必要とされている、誰かの役に立てているという達成感を日々実感することや、より人生の琴線に触れる会話を増やしていくことがこれまで以上に大切になっている、ということではないかと思います。
今後もそのような取り組みを米国で調査しBlogで発信できればと思いますし、このBlogが少しでも役に立ったと感じてくださった方が一人でもいれば、私もとても嬉しく思います。
シリコンバレーの自宅にて