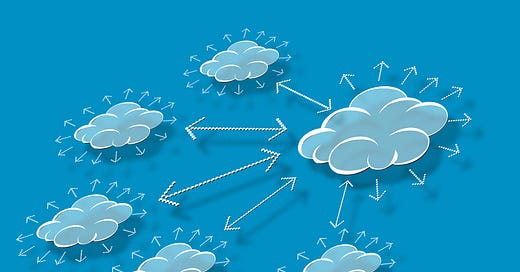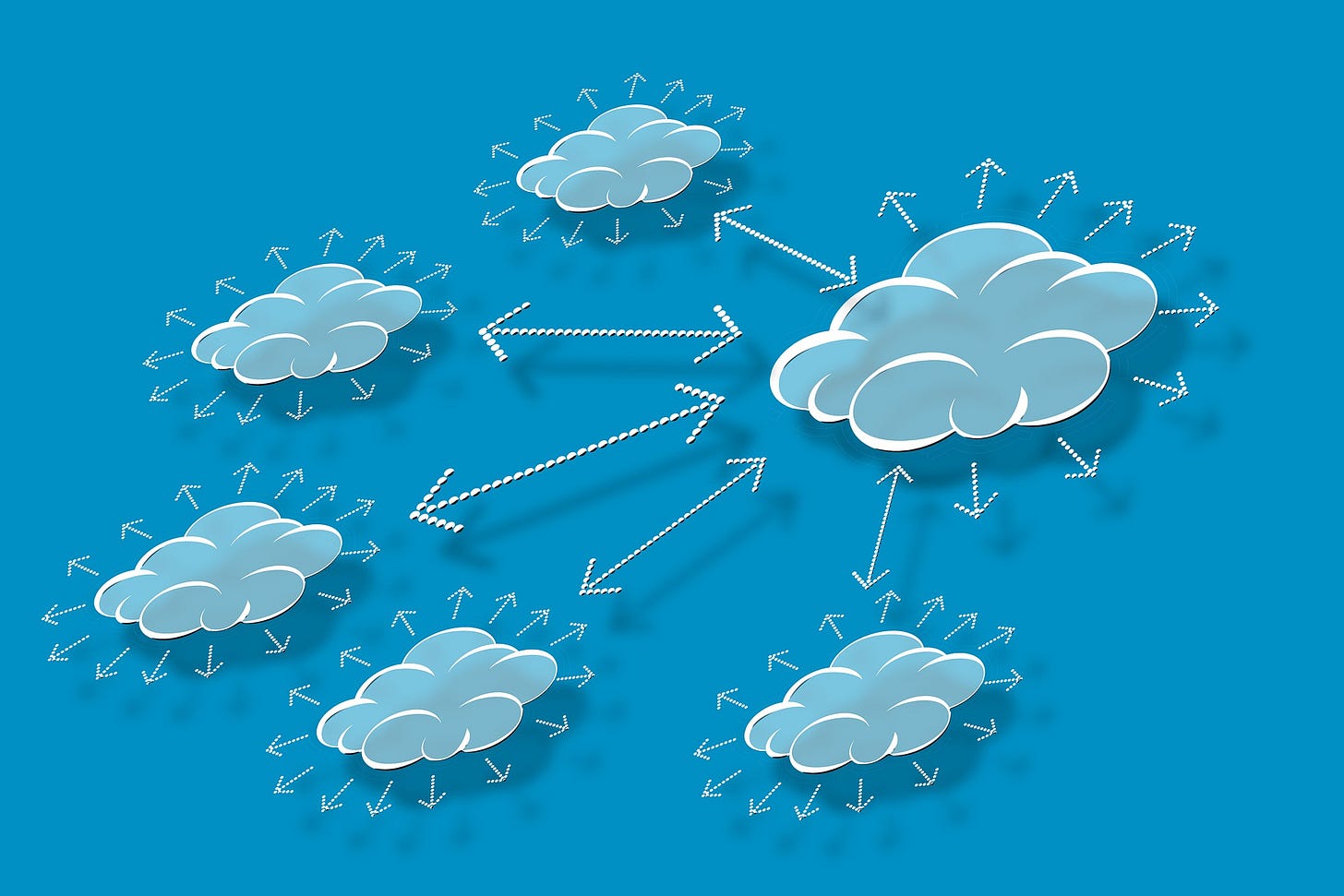クラウドコンピューティングは、柔軟性や拡張性など多くのメリットがありますが、大規模なインフラの場合にはコストが高くなることや、データ取り扱いに関する規制があることもあります。そのため、物理インフラを維持することも重要です。そこで、ハイブリッドクラウドが登場します。これは、企業のインフラとパブリッククラウドのリソースを組み合わせることで、容易に拡張性の高いリソースを利用できるようになり、企業にとって非常に魅力的な選択肢となっています。
Google、Amazon Web Services(AWS)、そしてマイクロソフトの3社は、高度に自動化され、集中化されたクラウドインフラを提供することで効果を発揮してきました。しかし、集中化による利点には、回復力、冗長性、パフォーマンス、規制に関しての弱点も存在します。そのため、クラウド3社は、エッジにクラウド環境を展開する戦略を取っています。エッジとは、一般的にIOTなどが接続する環境がイメージされますが、今回は企業のデーターセンター接続も合わせて紹介していきます。それぞれの3社のエッジ戦略を含めたハイブリッドクラウド戦略を比較していきましょう。
AWSのLocal Zone と Outposts
Local Zoneとは、AWSが特定の地域にインフラストラクチャーを展開し、ユーザーがAWSの提供するインフラストラクチャーを利用できるサービスです。ローカルゾーンを使用することで、ユーザーに近い場所でアプリケーションを実行し、レイテンシーの影響を受けにくくすることができます。また、データを特定の地域から出さないようにすることもできます。AWSはこのLocal Zoneに力をいれており、2019年に開始してから、すでに(2023年3月時点)世界中の32拠点に拡大しました。また18カ国21都市でローカルゾーンを展開する予定をしています。
AWS Outpostsは、オンプレミスまたはコロケーション環境に設定済みのAWSハードウェアを導入することで、AWSのクラウドサービスを現地で提供するためのサービスです。これにより、顧客は自社の環境内でAWSのサービスを利用することができます。
AWSは、ローカルゾーンとOutpostsを組み合わせることで、顧客が最適なクラウド環境を選択し、必要に応じてハイブリッドクラウド展開を行うことを可能にしています。ただし、AWSは自社のクラウドサービスを推進しており、複数のクラウドプロバイダーへのアクセスや企業が持つデータセンターのハイブリッドクラウド化についてはあまり積極的ではないようです。
Googleの Google Distributed CloudとAnthos
Google Anthosは、Kubernetesを使用して複数の環境にわたるアプリケーションを管理します。ハードウェアに依存しないこのサービスは、物理サーバーや仮想マシン上で実行することができ、あらゆるデプロイメントに適しています。顧客は、Google Cloudを利用した単一のコントロールプレーンからアプリケーションを管理しながら、好きなクラウドサービスにアプリケーションをデプロイ、実行、管理することができます。
Googleは、エッジやデータセンターでAnthosを利用できるようにするために、Googleの専用アプライアンス製品を提供したり、データセンターにある既存のインフラにソフトウェアをインストールしたりすることで、サービスを提供しています。このサービスはGoogle Distributed Cloudと呼ばれています。
Kubernetesに注力しているため、コンテナを積極的に利用している企業にとっては特に有用です。一方で、コンテナを多用していない企業にとっては、最適な解決策とは限りません。
マイクロソフトのAzure ArcとAzure Stack HCI
マイクロソフトはGoogleと似た戦略をとっています。AWSのようにエッジクラウドを建設していくのではなく、すでに既存である顧客の環境にAzureを構築することでクラウドを延伸しています。
Googleはコンテナに特化していましたが、Azureではコンテナだけでなく仮想サーバもAzure管理ポータルでオンプレミス環境をAzureのリソースとしてデプロイ、実行、管理ができます。Azure以外のクラウド環境における仮想サーバはエージェントを入れることでAzureポータルから管理が可能となります。また、KubernetesであればGoogleのAnthosと同じようにクラスタをアタッチするだけでマルチクラウド・ハイブリッドクラウド環境の管理もできます。
Azureハイブリッドのインフラ提供サービスをAzure Stack HCIと言います。ハイブリッドクラウドとKubernetesの管理をするサービスをAzure Arcと呼んでいます。
Azureで管理するための物理機器の提供方法は現在のオンプレミスの機器調達に近い感覚です。具体的にはAzure認定のサーバをWebカタログから選択します。パートナーベンダー複数、機器も数種類ありサーバをマルチベンダで構成できるように考えられています。またスイッチもAzure推奨機器が列挙されており、CiscoやJuniperなどサーバ以上に多くのベンダー、種類から選べるようになっています。
推奨スイッチには、データーセンター向けのハイエンドスイッチが並んでいたことから、データセンターに対して積極的にAzureクラウドを延伸していくという意図を読み取ることができます。
Azure Stack HCIをオンプレミス環境に導入する場合、基盤となるハイパーバイザはMicrosoftのHyper-Vを使用し、構築にはPowerShellを利用する必要があります。しかしながら、2020年の時点でハイパーバイザのマーケットシェアでは、VMwareが46.4%、Microsoftは2.7%であり、Hyper-Vを利用したことがない企業にとってはハードルが高いかもしれません。
しかし、Azure Stackは2022年10月からプレビュー版としては、vSphereを利用可能にしており、このことから、データセンタとのハイブリッドクラウドを考慮する際には、Azureがクラウド3社の中で最も優位な選択肢であると言えるでしょう。
まとめ
クラウド3社側の視点から、データセンターとのハイブリッドクラウドの取り組みについて見てきましました。ハイブリッドクラウドを利用することで柔軟性や拡張性以外にもオンプレミス環境からパプリッククラウドの各サービスと連携できることも大きな魅力の一つです。接続のしやすさだけでなくどんなサービスを使いたいかも重要になってきます。