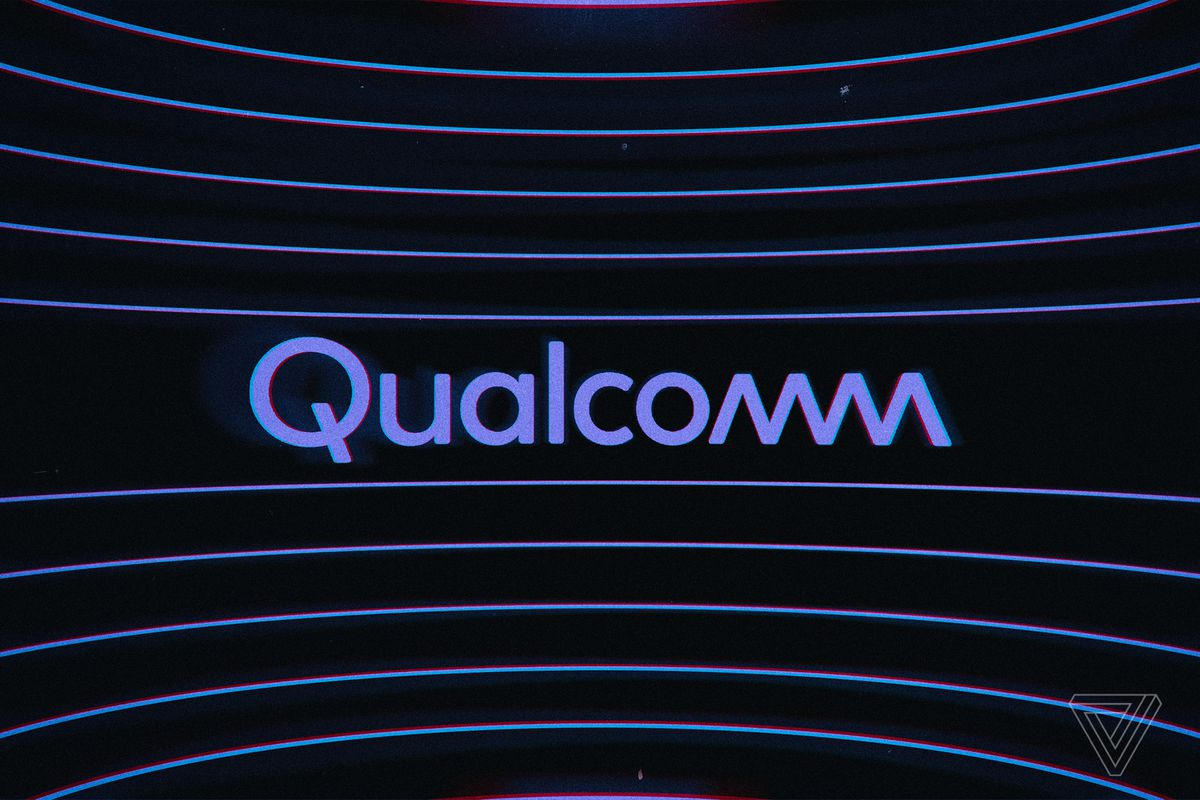Weekly newsletter #13
先週は連邦議会議事堂にトランプ支持者が乱入した事件に触れましたが、その後はトランプ大統領に対して一斉に非難や攻撃が激しくなりました。主たるSNSはアカウントの削除や永久追放、史上初の2回目の弾劾訴追。弾劾決議は下院議会では可決されましたが、上院議会は意図的に1/19までに召集しない状況になっているので、決議されないまま1/20の大統領就任式を迎えることになりそうですが、就任式を控えた議事堂の警戒態勢は異様な光景です。写真は議事堂内で休憩をとる州兵ですが、今週州兵は約7,000人配備され、最終的には2万人の州兵がワシントンに展開されるとのことです。議事堂を襲撃した支持者のうち逮捕者は既に100名を超えていますが、もっと過激化した人達が1/20に登場しないことを期待したいと思います。
さて、今週は世界最大のデジタル技術の見本市「CES2021」が開催されました。2000社以上の出展社が様々な最新技術を披露する場であり、従来は広大な展示会場を活かした様々な動体展示物が注目を集める催しでしたが、今回はオンラインのみの開催であったために例年とはかなり勝手が違ったようです。出展者や参加者からも大きな戸惑いの声が聞かれました。
今回、下記ではCESのニュースは取り上げていませんが、政治や世界情勢の変化だけでなく、それらに影響され変化していくビジネスやテクノロジー、大きな変化だけでなく、小さな変化の兆候も見逃さずにここで取り上げていきたいと思います。
Intel は新CEOにVMWareのパトリック・ゲルシンガーを指名
IntelはVMWareを大きく成長させたPat Gelsingerを新CEOとして迎え入れる。Gelsingerは元々Intel出身でかつてはCTOも務めていた。今のIntelは、ナノチップの開発競争においてTSMCやサムスンに遅れを取り、AMDやNVIDIAに市場を取られているという苦境に立っている。技術的に明るいGelsingerがこの状況をどのように打開していくのか注目される。
https://edition.cnn.com/2021/01/13/investing/intel-new-ceo-pat-gelsinger/
Qualacomm は、元Appleエンジニアが設立したスタートアップNuviaを14億ドルで買収
半導体市場は今まさに大きな変化が起こっている。AppleがIntelからARMベースの度独自のApple Siliconへ切り替えたように、Microsoftも独自チップを開発していると報道されている。かつてのパートナーが競合になりつつある状況で、次世代の5Gコンピューティングを意識した独自のチップコアに注力していくとのことだ。
Visa は司法省の異議申し立てにより、Plaidの買収を断念
VisaはAPIフィンテック・スタートアップの代表格である「Plaid」を53億ドルで買収する計画だったが、独占禁止法に抵触するとして司法省から異議申し立てを受けていた。オープンバンキングの発展を踏まえ、APIの重要性が高まっている中で、この買収を断念することはVisaにとっても大きな痛手だろう。MastercardによるスタートアップFinicityの買収は承認されていることから見ても、Plaidのポジショニングはもっと大きかったのだろう。
https://finance.yahoo.com/news/visa-v-plaid-terminate-merger-164504244.html
Google は米国、オーストラリアの規制当局の調査が続く中、Fitbitの買収を完了させた
GoogleはスマートウォッチのFitbitの買収を完了したと発表した。これまで独占禁止法の疑いで各国の規制当局から買収が承認されておらず、EUはようやく12月に承認したばかりだ。米国司法省とオースラリアの競争消費者委員会はまだ承認していないにも関わらず、このような発表をするのは異例なようだ。承認の見込みがあって先走っただけなのか、GAFAに厳しい民主党政権に変わる前に既成事実を作ってしまおうと動いたのかどうかは定かではない。
Amazon は貨物ネットワーク拡充のため航空機を購入
Amazonは貨物用ジェット機を既に11機所有しているが、さらに11機の中古ボーイング767-300を購入する計画だ。2022年末までに全世界で85機以上の航空機を持つ予定だが、今後数年間で200機まで増やし、UPS(米国郵政公社)に匹敵する空の貨物ネットワークを構築するだろうと言われている。
Walmart はRibbit Capital とフィンテック企業を設立
小売最大手のWalmartは、従業員と顧客に向けてユニークで手頃な金融商品を開発するためにフィンテック企業を設立する。従業員だけでも全世界で230万人、それに加えて数百万人の顧客に向けた金融サービスは、決して裕福層ではなく、手数料無料や家計管理などの庶民に優しいサービスを提供していくものだと思われる。