Weekly newsletter #20
「ネット中立性」という言葉を生み出したコロンビア大学のティム・ウー教授がバイデン政権に加わりました。ネット中立性とは、政府やインターネットプロバイダーがネットワークを通過するデータを平等に扱い、特定のWebトラフィックを抑制したり、人気のあるサービスへのアクセスに追加料金を請求したりしないことなどを示す原則で、通信業界の規制に関する議論の中心にある考え方です。しかし、ウー教授が最も注目を集める理由は、ビッグテック企業に対する積極的な独占禁止法の執行を主張している人物だからです。GAFAMのような企業は、大きくなりすぎて競争が不足していると主張しています。民主党の左派でビッグテック解体論者のエリザベス・ウォーレンやバーニー・サンダースが歓迎して政権へ迎え入れてると思われます。
「ネット中立性の父」であるティム・ウーがバイデン政権に加わった
今週のトピックスのように、ビッグテック企業が関わるプライバシーやセキュリティの話題には事を欠きません。欧州や米国内でのビッグテックへの風当たりは年々強くなってきていますが、その間に中国におけるAIを初めとしたIT投資の勢いは増しています。現在、AI国家安全保障委員会の議長を務める元GoogleCEOのエリックシュミットは、米国におけるAIの研究開発への投資を倍増、技術者の育成などへの早急な手当が必要だと警笛を鳴らしています。ビッグテック企業の解体が行われるようなことになれば、まさに安全保障上の問題になり兼ねないのではないでしょうか。また、消費者保護も大事ですし、寡占や独占を引き起こしている状態は健全ではありませんが、規制や訴訟によってイノベーションが滞ることのないようにして欲しいものです。
AIに関する国家安全保障委員会が米国の優位性を維持するための報告書
OktaがAuth0を65億ドルで買収した理由
ID管理のOktaがAuth0を買収した。ID管理市場の競合買収という見方をしがちだが、Oktaは企業の従業員向けの認証用途であるのに対し、Auth0は開発者向けに認証APIを提供している。Oktaは買収により、従来カバーできていない一般消費者や中小企業向けの認証プラットフォームへと拡大していくことになる。ゼロトラストセキュリティで注目を集めるようにID管理はますます重要な位置付けになっていくでしょう。
https://supertokens.io/blog/the-real-reason-okta-spent-on-auth0
GoogleはCookieを廃止し、新しい追跡技術を採用しないと主張
GoogleはChromeでのサードパーティCookieを2022年までに廃止すると発表。個人のWeb閲覧履歴に基づくターゲティング広告が出来なくなることを意味するが、代わりに「匿名化した集約属性のコーホート」を用いてユーザーデータを分析することを検討しているという。これは、FLoC(Federated Learning of Cohorts:連合学習コホート)と呼ばれ、収集した閲覧情報を匿名化された類似の閲覧集団としてグループ化して、所属グループを「コホートID」としてウェブサイトや広告主と共有するものである。個人特定しなくとも属性に基づいたターゲティング広告は可能ということになる。EFF(電子フロンティア財団)は「FLoCは最悪な考えだ」と表現し、属性の大きさやログイン情報などと結びつけて個人追跡も可能、加えて属性に基づく広告は、民族や宗教、性別などの差別的な広告の温床になることに変わりはないと反対を示している。
https://techcrunch.com/2021/03/03/google-renounces-ad-tracking/
Facebookがイリノイ州のプライバシー保護法をめぐる集団訴訟で約694億円支払う
Facebookは、イリノイ州住民をプライバシー侵害から守る州法 Biometric Information Privacy Act(BIPA:生体認証情報プライバシー法)に違反したとして、160万人のイリノイ州住民に1人あたり345ドル(約3万6800円)以上支払うことを命じられた。Facebookが顔認識を利用して写真の中の人に同意なくタグを付けていることがこの州法に違反していると告訴されたのだ。さらに、Microsoft、Google、Amazon、Cleatviewなども同様に個別に告訴されている。欧州を含めてプライバシー保護に関する規制は厳しくなっているが、米国内においても州ごとに規制や法律が大きく異なるのは、テクノロジー企業にとって大きな脅威である。
https://jp.techcrunch.com/2021/03/03/2021-03-01-facebook-illinois-class-action-bipa/
Microsoft Exchangeサーバーの脆弱性を中国ハッカーが攻撃
中国を拠点としている「HAFNIUM(ハフニウム)」というハッカーグループがMicrosoft Exchangeサーバーを標的にゼロデイ攻撃を仕掛けていることが分かった。Exchangeサーバーの数は米国だけでも3万以上、世界中で数十万と言われ、1月から無差別に侵害がされており、甚大な被害規模になると見られている。SolarWindsのハッキング被害は18,000組織で、ロシアのハッカーグループの犯行だと言われているが、最近のこの手の攻撃は大規模且つ巧妙さを増しており、明らかに国家の安全保障に関わる問題として取り組む必要性が鮮明になってきている。
https://www.wired.com/story/china-microsoft-exchange-server-hack-victims/
MicrosoftのMeshは、リモートにいる同僚をホログラムに変える
Microsoft Ignite 2021 にて、ARヘッドセットのHoloLensを使った仮想コラボレーションのアップデートが紹介された。Microsoft Meshでは、ホログラフィックアバターが物理空間に表示され対話が可能となる。リアルな人物を表示する「ホロポーテーション」の場合には、外部センサーなどを使って人の動きをキャプチャする必要があり、まだ気軽に利用は難しいようだが、自宅に同僚が現れて打ち合わせする映像はかなり未来感がある。
https://www.popsci.com/story/technology/microsoft-mesh-holographic-mixed-reality/
Azure Perceptは、エッジAIを最大限に活用させる
Azure活用に加えてエッジコンピューティングの強化として、Azure Percept(知覚)と呼ばれる各種ハードウェアが登場した。画像や音声認識が可能なハードウェアとAI機能を一元化した開発キットとして提供される。工場や遠隔地のIoTデバイスのコントロール用など、様々なエッジの高度化が期待できる。
https://techxplore.com/news/2021-03-azure-percept-microsoft-users-edge.html









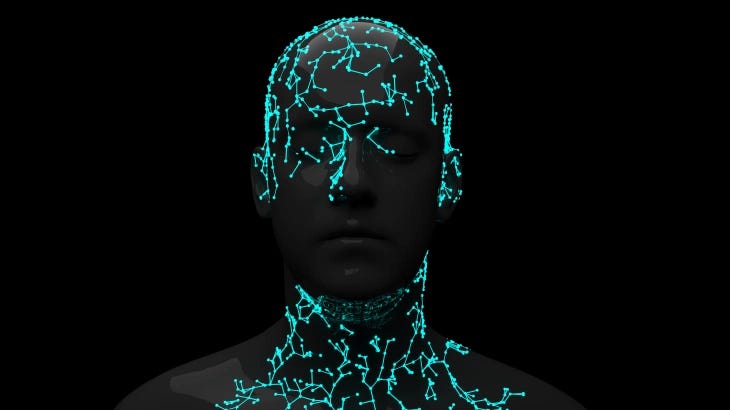

![[Sarah Katz] Azure Perceptは、MicrosoftユーザーがエッジAIを最大限に活用するのに役立ちます [Sarah Katz] Azure Perceptは、MicrosoftユーザーがエッジAIを最大限に活用するのに役立ちます](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!wi-C!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fdf8e62e5-471d-4db3-8a23-a1f9ea8221ea_730x410.jpeg)