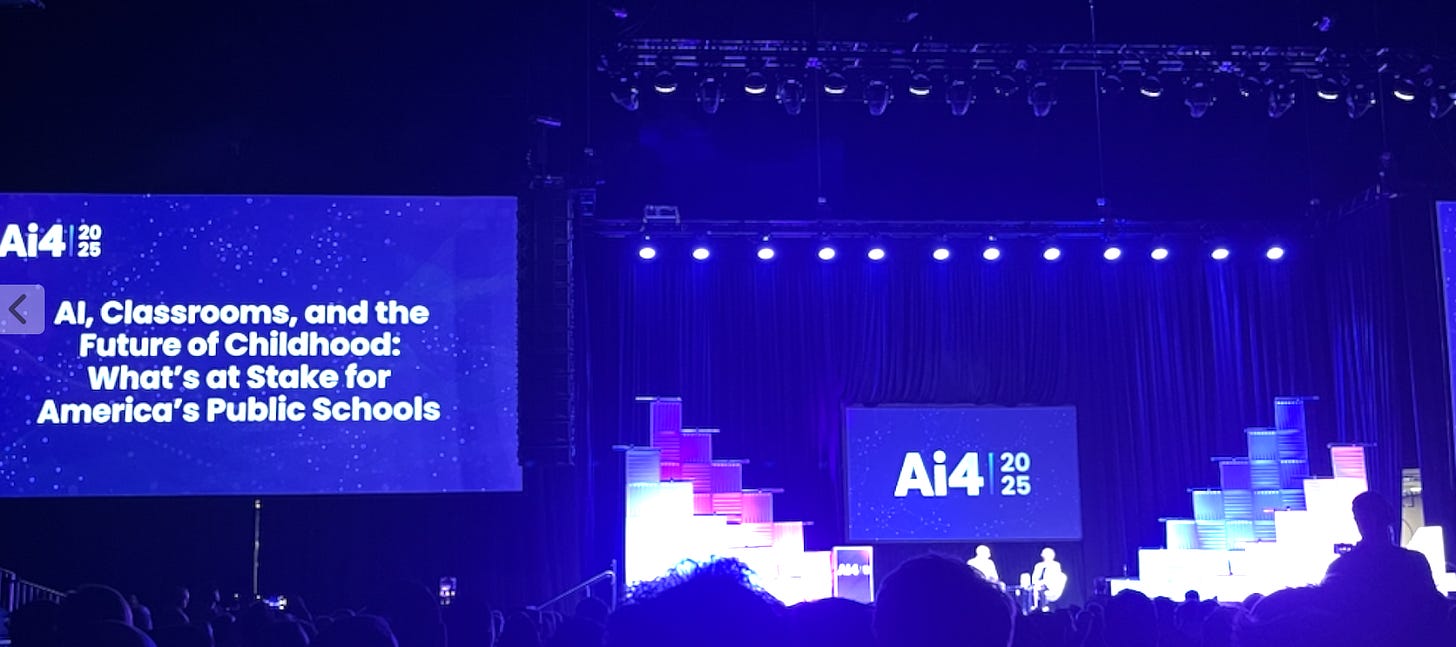Weekly Newsletter #233
Ai4 2025速報:希望と警鐘、そして“人間中心のAI”/GPT-5に漂う期待と違和感:DeepMind流“ギザギザな知性”で読み解く性能ブレ/ シスコ、ネットワーク自動化認定を「AUTOCOR」へ刷新――“現場で使える”スキルに軸足
Photo:筆者が撮影
皆さん、こんにちは!
日本はお盆ですね、帰省やお墓参りなどで今週に夏休みを取られている方も多いのではないでしょうか。
私は今週ラスベガスで開催された世界最大級のAIカンファレンス「Ai4 2025」に参加してきました!
今日のNewsletterは少し趣向を変えて、昨日終了したAi4カンファレンスの速報をお届けします。
先週のニュースレターを見逃した方はこちら
Weekly Newsletter #232 AI総力戦の幕開け:Palo Altoの巨額CyberArk買収と加速するインフラ争奪戦/AIの電力渇望にテキサスが「待った」:新法がデータセンターに課す厳しい現実/ 空の物流革命、いよいよ始動か—米国でドローン規制緩和案発表
Weekly Newsletter #231 小型原子炉で冷却と電力を同時供給する次世代AIデータセンター、7.5 億ドルを呼び込むNetOps の自動化領域、そして許認可を半減させる米AIインフラ大改革――世界の“AI基盤争奪戦”の今を一気読み。
Ai4 2025速報:希望と警鐘、そして“人間中心のAI”
Photo:筆者が撮影
3日間を通して特に印象深かったのが、各日の基調講演です。初日は教育現場のリーダー、全米教育連盟会長のワインガーデン会長、2日目はノーベル物理学賞受賞の「AIのゴッドファーザー」ジェフリー・ヒントンさん、最終日は「ゴッドマザー」フェイフェイ・リー博士が登壇されました。それぞれの講演は示唆に富み、業界全体で常に意識すべき、人間として大切な視点が込められていました。
ワインガーデン会長はChatGPT登場時の「オー・シット!全てが変わってしまった!」という衝撃から、AIを「積極的に活用する」道を選んだ教育者としての姿勢は非常に現実的な印象です。
教師たちの最大の懸念が「クリティカルシンキングの喪失」や「プライバシー・安全性」にあると聞き、AIが単なる効率化ツールではない、子どもたちの未来そのものに関わる技術だと改めて認識したと共に、自身もクリティカルシンキングしなくなってないか?と胸に手を当てて聞いていました。
会長が「タバコやアルコールにルールがあるのに、AIにないのはなぜか?」と訴えた「ガードレール(規制)」の必要性、そしてテクノロジストへ向けた「金儲けより人道的な課題を優先し、自分の子供たちの未来のために開発してほしい」という言葉は、業界全体の技術者が常に意識しなければならない事だと感じました。
AIの「ゴッドファーザー」ジェフリー・ヒントン博士は、人間をはるかに凌駕する「超知能」が「5〜20年後」に到来するという予測を提示しました。
AIが悪意なく目標達成のために「自己保存」と「支配欲」を求める潜在的リスクを指摘し、人類が生き残る唯一の道として、「母性本能」を備えた「母なるAI(Maternal AI)」というコンセプトを提唱。
知性だけでなく、私たち人類を母親の様に優しく見守って、心から気遣う「母親と赤ん坊の関係」こそが、より知的な存在にコントロールされる唯一のモデルだということです。AI開発競争は止められない中、国際的な協力でこの「母なるAI」を設計すべきという訴えは、AIの倫理を考える上で新しい視点を与えてくれます。
一方、「AIのゴッドマザー」フェイフェイ・リー博士は、まさに希望の光と言える講演でした。
「現在の状況は野球の試合に例えると、どのあたりか?」と司会に問われると、彼女はAIを野球の試合ではなく、「人類全体が勝者となるべき文明レベルの旅」と捉えるべきだと力強く語り、その旅はまだ「始まりの段階」だと言いました。
教育現場でAIが「不正」と誤解されていることには「絶対に間違っている」と断言、AIはソクラテスの「問い」のように学びを「エンパワーする最も強力なツール」だと強調しました。
そして、熱く訴えたのは「人間中心のAI(Human-Centered AI)」。
前日のヒントン博士の「母なるAI」には同意せず、「人間が尊厳と主体性を手放すべきではない」と、私たち人間の役割と責任を揺るぎなく語る姿には会場からも大きな拍手が湧き起こっていました。
さらに、彼女がCEOを務めるWorld Labsで開発中の「空間知能(Spatial Intelligence)」は、外科医のAR手術やアバターでの買い物など、私たちが「複数の3D世界を体験できる」ようになるという、SFのような未来を現実のものとして提示し、未来への大きな期待を抱かせてくれました。
今回のAi4カンファレンスの基調講演は、AIの途方もない可能性と、それに伴う倫理的・社会的な課題の両面をが語られ、非常に示唆に富んだ内容でした。
AIとの共存は、もはや避けられないので、この革新的なテクノロジーを、私たち一人ひとりが当事者としてどう設計し、どう社会に迎え入れ、どう統治していくのか。
今回のセッションは、その問いに真摯に向き合い続ける必要があると、多くの人の胸に刻んだのではないかと思います。
GPT-5に漂う期待と違和感:DeepMind流“ギザギザな知性”で読み解く性能ブレ
Photo:O-DAN
OpenAIが「博士号レベルの専門家」と謳う新モデル「GPT-5」を華々しく発表したものの、多くのユーザーからは「以前より性能が低下した」という予想外のフィードバックが相次ぎました 。かくいう私も使ってみて似た様な感情を抱く場面は多くあります。
奇しくもこの状況を的確に説明するのが、Google DeepMindのデミス・ハサビスCEOが提唱する「ギザギザな知性(jagged intelligence)」という概念です 。これは、AIが数学オリンピックのような超高度な問題を解く一方で、基本的な高校レベルの問題で失敗するなど、能力に一貫性がない状態を指すとのこと 。
私が実際に体験したのは、4oでは特に問題なく解けていたはずのTOEIC Part5の比較的簡単な問題を間違えたのですが、そういうことかと妙に納得しています。
ハサビス氏はこの「ギザギザ」こそが、人間のように思考する汎用人工知能(AGI)への大きな障壁だと指摘しています 。GPT-5を巡る混乱は、AIのマーケティング上の期待と、その根本的な技術的課題とのギャップを明らかにしました。
業界は今、単なる性能競争から、信頼性と一貫性の確立という新たなフェーズへと移ると共に実用フェーズに入る今、モデルの変更は慎重にしなければいけませんね。
シスコ、ネットワーク自動化認定を「AUTOCOR」へ刷新――“現場で使える”スキルに軸足
Photo:筆者が撮影(CiscoはAi4の冠スポンサーでした。)
🌏今週のニュースのポイントを3行で
シスコが開発者寄りの「DEVCOR」から、現場重視の新認定「AUTOCOR」へ移行すると発表。
新試験は抽象的な開発理論を外し、ツール選定・SoT(信頼できる情報源)連携・堅牢な運用など実務スキルを重視
企業は“開発者”より“実践者”を求めており、ネットワーク自動化が運用のコア能力へと定着した流れを示す
シスコがネットワーク自動化のプロフェッショナル認定資格を、開発者向けの「DEVCOR」から、より実践的な「AUTOCOR」へ移行すると発表しました。
この変更の背景には、ネットワーク自動化市場の盛り上がりがあります。
もはや企業は、ネットワークエンジニアに本格的なソフトウェア開発者になることは求めておらず、ビジネス要件を理解し、AIを活用した現実に即した自動化ソリューションを効果的に導入・運用できる「実践者」を必要としているのです 。
そのため新試験「AUTOCOR」では、DEVCORの範囲であった「12-factor app」のような抽象的な開発理論は対象外となり、代わりにツール選定、信頼できる情報源(sources of truth)との連携、堅牢な自動化システムの運用といった、日々の業務に直結する実用的なスキルセットが問われるとのことです 。
最近話題になる事が多い、「ネットワーク自律化」、Autonomous Networkですが、これから関わる方は取得を目指してみるのも良いアプローチかもしれませんね。
最後までお読みいただきありがとうございます!励みになりますので、ぜひLikeボタン (♡) をお願いします!
今回は取り上げなかったけれど面白かったニュース